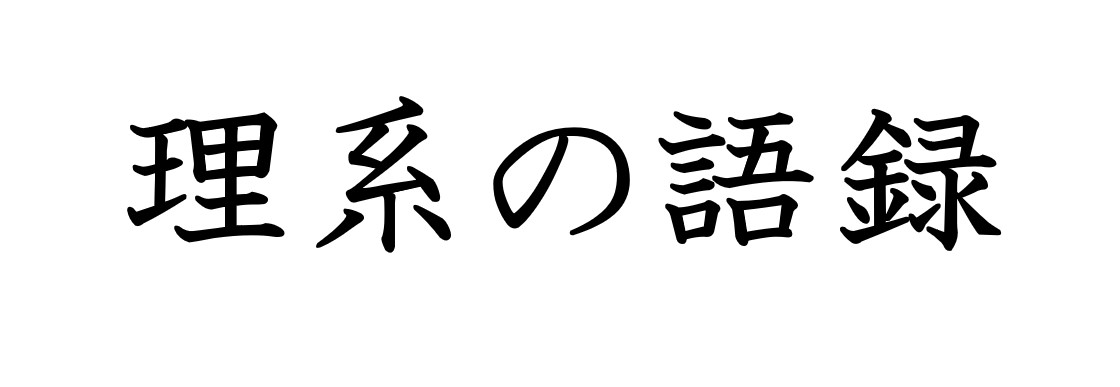はじめに
この記事では仕事を効率化するツールとしてマインドマップを紹介します。
仕事をする上で必須になる作業がメモや議事録作成、プレゼン資料作成などです。
それらすべての質を高めて、なおかつ仕事の効率化もできるITツールがマインドマップです。
今回は仕事上で活躍するシーンや基礎的な使い方、おすすめの無料ソフトまで紹介します。
特に資料作成が苦手、プレゼンが上手くできないという人はマインドマップを一度活用してみることをおすすめします。
マインドマップとは

まずマインドマップとはどのようなものなのか簡単に解説していきます。
マインドマップという単語を初めて聞いたという人や一度も使ったことがないという人は、まずマインドマップはどのようなものか知るだけでも有益だと思います。
マインドマップを使うことによるメリットもまとめているので、読んだ後にはマインドマップを使ってみたいと思うこと間違いなしです。
マインドマップの発祥と概要

マインドマップの発祥
今はマインドマップはITツールとして認知されていますが、そもそもは「思考の表現方法」として提唱されたものです。
イギリスの著述家で教育コンサルタントも務めていたトニー・ブザンが脳科学や心理学の知見から50年以上前に考案しました。
本来は紙とペンで思考を放射状につなげていくことで思考をマップ状に表現する手法です。
現代においては、PCやスマホ・タブレット上でマインドマップが描けるソフトウェアやアプリが数多く登場し、IT業界を中心とするビジネスシーンで多く活用されています。
マインドマップの概要
マインドマップは頭の中の思考を脳の内部に近い形に描き出すことができます。
基本的には用紙の中心にメインのキーワードやテーマを書き、そこから関連するキーワードを分岐させて広げていくものです。
考えをマップ状に「見える化」することで、論理的な思考や新しい連想をすることができます。
マインドマップは頭の使い方という意味でのメンタルリテラシーに適した思考法であり、ツールです。
マインドマップのメリット
マインドマップを使用することのメリットは脳科学や心理学の面からも多くが認められています。
記憶能力の向上
物事を脳の内部構造と近い形で表現するので、記憶に定着がしやすいです。
また、短い単語や文章で視覚的に具体化することができるので、複雑内容に対しても記憶に残りやすく理解力が高くなります。
ひと目で全体が把握可能
関連するキーワードや内容が一枚のマップの上にまとまることでひと目で全体が見渡せます。
これにより課題の全体像を俯瞰して掴むことができたり、新たな気付きや発見が見つけやすくなります。
また、全体を言葉で説明することなく短時間で他人と共有できるという点も全体が見渡せるマインドマップ特有のメリットです。
マインドマップの作り方は初めてでも簡単

マインドマップを描くときに最低限知っておきたい基礎知識や基本ルールを解説します。
ここで紹介する内容はあくまでも一般的なマインドマップで基本ルールとされている内容です。
「綺麗に規則通りにマインドマップを作ることが本来の目的ではない」ので、ポイントだけ押さえて実際にマインドマップを作成してみてください。
ここでまとめた基本ルールを頭の片隅に入れて、実際に使ってみることでマインドマップの効果を実感できます。
基本的なマインドマップの構成
マインドマップを構成する基本要素は「トピック」と「枝」です。
中心に主題のテーマを書いたら、それを中心に連想される関連キーワードや図や絵などの「トピック」を「枝」でつなげていきます。
伸びた「枝」から連想される「トピック」があればまた「枝」を伸ばしてマップを広げていきます。
この作業を繰り返すことでマップが放射状に広がっていき、全体像を描くことができます。
完成されたマインドマップを見ることで、思いもしない関連性や解決策が浮かぶこともあり、発想力や理解力、記憶力が高まります。
マインドマップの基本ルール
マインドマップを作成するには柔軟で自由な発想が大切ですが、その思考力を正しく発揮するために基本ルールとされていることがあります。
12のルール
マインドマップを提唱したトニー・ブザンによる「12のルール」があります。
- 無地の紙を使う
- 用紙は横長で使う
- 用紙の中心から描く
- テーマはイメージで描く
- 1つのブランチには1ワードだけ
- ワードは単語で書く
- ブランチは曲線で
- 強調する
- 関連づける
- 独自のスタイルで
- 創造的に
- 楽しむ
(引用元:Wikipedia「マインドマップ」)
しかし、現在普及している書籍やツールにはこの12のルールに当てはまらないものも多くあります。
あくまでも基本ルールであるので、取り上げるテーマや用途に応じて「10. 独自のスタイルで」マインドマップを活用すると良いでしょう。
自由に使うと発想が広がる
この後にも紹介しますがマインドマップを使えるシーンは多様です。
「論理的思考」に加えて、「想像力」「発想力」も発揮することができるのがマインドマップです。
そのため、シーンに合わせて自由な使い方で工夫をこらすことでよりマインドマップのメリットを強調することができます。
自由な使い方を繰り返すことで発想が広がり、マインドマップを使う方法もレベルアップしていけます。
仕事でマインドマップが活用できるシーン

基本的にマインドマップを主に使う場面としては仕事が多いです。
具体的に仕事のどんなシーンでマインドマップが活躍するかと、それぞれのシーンで使うときの注意点を解説します。
うまく活用することで会社でも頭一つ抜けた成果を出すことができるかもしれません。
ブレインストーミング
ブレインストーミングとは、数人でアイデアを出し合うことで新しい発想や解決策を抽出する技法です。
ブレインストーミングにはマインドマップが非常に有効です。
マインドマップがブレインストーミングに適している理由は、下記に示すブレインストーミングの基本ルールにマッチしているからです。
- 結論厳禁
- 自由奔放
- 質より量
- 便乗歓迎
マインドマップを使ってブレインストーミングを行うときには、Webサービスやソフトウェアを使うことをおすすめします。
マインドマップのソフトやサービスにはWeb上で共有して、複数人で同時に編集できるものもあります。
従来は会議室などで集まって行うことが多かったですが、リモート環境でもブレインストーミングが簡単に行うことがでできます。
また、紙の用紙と違い記入できる領域も無限大に広いので、アイデアをたくさん出すことが求められるブレインストーミングには最適です。
企画
マインドマップを使うときの本質は「連想」です。
連想や想像力は新しい企画を練る段階で必要な要素の一つです。
マインドマップで関連するキーワードを広げていくことで、今まで想像していなかった分野とのシナジーが見えてきたり、リスク抽出ができます。
企画段階でマインドマップで作成したら、その全体を一度眺めてみてください。
たくさんの「枝」が伸びている部分や「トピック」が明らかに多い部分があると思います。
その部分が企画におけるストロングポイントであり、収益を上げることができるターゲットであることが多いです。
また、企画の中心からの距離も視覚的に分かるので、スケールアップするときの順序なども勝手に整理されてマインドマップ上に表現されています。
特に企画を立ち上げる初期の段階でマインドマップを作成すると効果的です。
議事録
議事録を作成するときにWordやExcelなどを使っていることが多いと思いますが、マインドマップを使うことでより簡単に明確な議事録を作成できます。
マインドマップで議事録を作成するときのポイントは3つあります。
- アジェンダと議題は明確にする
- 文章は短く、できるだけキーワードで記載
- 最後に決議事項を整理
まずマインドマップで議事録を取る際には、中心に議題を主題として書きます。
そこから議論の内容をトピックごとに放射状に広げていきます。
そのため、アジェンダや議題が明確ではない会議ではマインドマップでは議事録がうまく取れません。
その際にはブレインストーミングみたいに全員で共有して使ったほうが有効です。
マインドマップで議事録を作成すると、決議事項や重要な内容がどこに記載されているかわからないときがあります。
そのため、会議の最後に簡単に決議事項をまとめたり、重要な部分には色付けするなどの工夫をすることで、よりわかりやすくなりなります。
学習ノート・メモ
マインドマップのメリットの「記憶能力の向上」という点を最大に生きる場面が勉強のときに取るノートです。
セミナーや授業のメモにマインドマップを使用すると、ノートを取るスピードが格段に早くなり、記憶にも残りやすいので非常に効果的です。
話の全体像を考えてマインドマップにする必要があるので、普段よりも脳をフルに回転させることができて集中力も高まります。
手書きのノートでマインドマップを活用するときには、3色ボールペンを使うことがおすすめです。
自分の考えや感想なども追記してみると、記憶に残りやすいので見直しをしたり復習をするときにもどんどんマインドマップを広げていきましょう。
プレゼンテーション
マインドマップをプレゼンテーションに活用するときには「下書き・草案を作成する」「プレゼン資料にする」2つの使い方があります。
スピーチやプレゼンテーションでは、伝えたい内容とその根拠が構造的に整理させていることが大切です。
マインドマップはまさに構造的に内容を整理することができるので、それらの下書き・草案を作成するときには最適です。
また、マインドマップのツールによってはプレゼンテーションモードで資料を作成することができ、マインドマップそのものをプレゼン資料として活用することもできます。
PowerPointを使用して資料を作ることに比較しても半分程度の時間でプレゼン資料が完成するので、業務の効率化もできます。
この後おすすめのソフトも紹介しますが、マインドマップを使ったプレゼンテーションをしたい人には「MindMeister」がおすすめです。
おすすめのソフト

ここまでマインドマップの基本的な内容や使い方の開設をしてきました。
マインドマップをより効率的に使うためには、手書きではなくツールを使うことがおすすめです。
ここでは数あるツールやソフトウェアの中から厳選したおすすめを2つ紹介します。
いずれも無料で使用できるプランがあるので、両方使ってみてどちらが使いやすいか試してみると良いでしょう。
XMind

「XMind」はPCにインストールして使用するツールです。
実際に使ってみた感想としては「シンプルなインターフェースで操作性が良い」です。
インストールして使用するソフトウェアなので、オフラインでも使用できるという点はメリットと考えられます。
そして、なんと言っても無料でもマインドマップの作成数に制限がなく、個人で使用するなら無料版でも十分な機能を備えています。
プレゼンテーションモードやガントチャートなどの機能を使用したい場合は有料版を購入する必要があります。
有料版は買い切りで「13,036円」で購入できます。 (2020年12月価格)
MindMeister

「MindMeister」はウェブブラウザ上でマインドマップを作成することができます。
データはクラウド上に保存され、上書き保存などをしなくても変更がある度に自動保存しているので、保存し忘れる心配がないです。
動作も非常に軽く、UIもポップで見やすいです。
複数人で共有できるリアルタイムコラボレーション機能や簡単にプレゼン資料が作れるプレゼンテーションモードが優秀で便利です。
無料版では3つまでしかマインドマップを保存することができませんが、メモに使う程度で使い終わったものから削除するのであれば問題ありません。
マップ数に上限がない有料版は月額で「540円」から使用できます。
登録後にアップグレード/ダウングレードもできるので、一度無料版から試してみることをおすすめします。
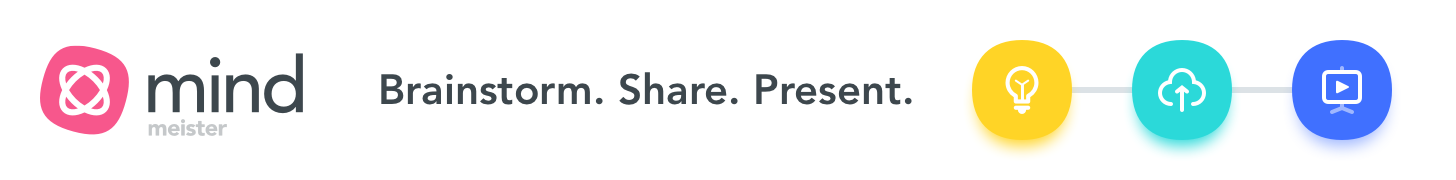
おわりに
今回は思考を表現する手法・ツールとしてのマインドマップを紹介しました。
本記事ではマインドマップのメリットや有効性にフォーカスしていますが、使う人によっては合わない人もいます。
例えば、抽象的な思考能力に長けている人や前提を覆す柔軟な思考が強い人はマインドマップを使うことが煩わしいと感じる場合もあります。
マインドマップは無料で使えるサービスも多いですし、紙とペンで作成することもできます。
一度実際に試してみて、自分に合っているか、どんなシチュエーションで使いたいかを考えてみることをおすすめします。