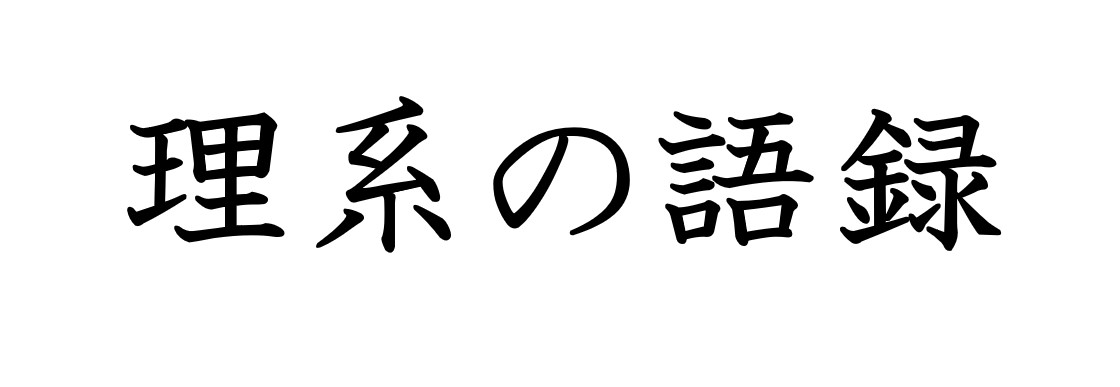はじめに
ES (エントリーシート)は就活のステップにおいて一番初めに書くものです。
そのため、ESでつまずいてしまうと就活はその先に進むこともできず、何もできずに惨敗してしまいます。第一希望の企業に合格するためにも、ESを通過するための必勝法を知ってESを書き上げましょう。
この記事には、実際に通過したESの事例も含んでいます。ちなみに私が就職活動をした時は、15社にESを提出してすべて通過、通過率100%でした。
そんな当時の経験と社会人になってからの視点を合わせて書かれてますのでかなり実用的な内容になっています。
ES通過の実績 (通過率100%)

論より証拠ということで、私が就活をした時のESの通過実績を紹介します。
私がESを提出した企業は以下の通りです。(現在私が働いている企業は省かせていただいています。)
- ANA
- KDDI
- MeijiSeikaファルマ
- オムロン
- オリンパス
- キッコーマン
- キリン
- 旭化成
- 伊藤忠エネクス
- 三菱重工
- 三菱電機
- 積水化学
- 日立製作所
- 村田製作所
- 日本電産
- 味の素
- 明治
通過率は100 % でした。つまり、上記の提出した企業はすべてESを通過しています。
私自身は大学では電気系の専攻でしたが、「機械」「食品」「医療」「商社」など様々な業種でエントリーしていました。そして、そのすべての業種で選考に残ることが出来ました。
なぜ私が自分の専門分野以外の企業においてもESが評価されて就活の選考に残ることが出来たかというと、下記の通りESを書いた結果です。
この実績から「必勝法」であると言っても過言は無いのではないでしょうか。
私の真似をすることで同じようにESが100 %通過するとは保証しかねますが、確実に通過する可能性が高くなることは保証します。
ES通過率を上げる必勝法

ESの通過率を上げる必勝法というと聞こえはいいですが、残念ながらこの内容を書けば必ず通るというESの答えは存在しません。
しかし、確実に通過率が上がる方法があります。
それは、「内容の質を上げること」です。
ESには文字制限が必ず存在しています。そのため、設問ごとに制限された数百文字の質の差で合否が判断されます。質を上げるための考え方、書き方を知ることでES通過率を飛躍的に向上させることができます。
まずはESを書き出す前に、ESを書く上での考え方の基本を知っていきましょう。
ESの内容を要因分析して研究する
まず、就職活動においてESを書くにあたって、初めはESをたくさん見ることから始めてみてください。
数多く企業はあれどESの設問の種類は限られています。必ずと言っていいほど聞かれる「志望動機」など多くの企業で共通する部分は対策が打てます。
具体的な設問ごとの対策は、この記事の後半に書いてありますので是非参考にしてみてください。この下にはESを書く上での持論を書いてますので、すぐに具体的な設問の対策を知りたい方は少し飛ばしていただければと思います。
ESを書くときに必ずやって欲しいことがあります。
それは、「自分が書いたESを残す」ということです。
文章を書く能力がある人は企業HPのES入力フォームに直接書き込む人もいるかと思います。もちろんこれでもESを通過する人はすると思いますが、この方法が良くない理由が2点あります。
1つは、面接で矛盾が生まれる可能性があるということです。ESが通過したからと言って内定までの道のりにおいてはたった一歩進んだだけです。ES通過後には基本的に面接があります。面接の場では面接官・人事の手元にあなたが書いたESがあります。そのため、面接での質問に対してESで書いたことと全く違うことを答えると矛盾が生じて、極論を言うと嘘つきと認定されます。これは非常にもったいないことなので、ESは記録に残して面接前に確認しましょう。
2つ目は、次のESに繋がらないということです。就活に臨むにあたってほとんどの人が複数の企業にエントリーすることになります。そのため何枚もESを書くことになります。そこで、ESの似た設問に対して書くときに一番参考にできるものは自分のESです。自分のESを読み直して、研究して改善していくことが文章をより良くすることには効果的です。
はじめからESや面接が上手な人は意外に少ないです。つまり、積極的に分析して改善していくことで他の志望者との差をつけることができるチャンスがあります。
コピペはNG!オリジナリティを出す
ESも含めた就活で一番心に留めておいてほしいのは「オリジナルで勝負する」ということです。
多くの人が過去の先輩が通過したESを参考にしてESを書こうとしているのではないでしょうか。参考にするうえでは過去のESは非常に有効です。
しかし、過去のESで参考にするべきなのは「文章の構成」「言葉遣い」など基本的な文章を書くための要素です。間違っても内容のコピペは絶対にしてはいけません。
コピペは楽ですし、それでもESは通過するかもしれません。しかし、コピペすることはリスクが大き過ぎます。
コピペすることのリスクは、一番はバレて落ちるということです。最近はESをHP上の記入フォームに書くことが多くなっています。そのため、企業側が過去のESをデータとして持っています。実際に導入されているかはわからないですし、知っていても言えないですが、AIやソフトを使うことで非常に簡単に文章の重複は見つけられます。理系の人で英語で論文を書いたことがある人なら引用のチェックなどをWebで自動でされた経験があるのではないでしょうか。簡単にふるいにかけられて落ちるのはもったいないので、コピペは絶対にやめましょう。
更に、コピペすることで過去と被るだけではなく、同期とESが被ることも可能性として考えられます。同じ先輩のESを持っている人は何人もいますし、その先輩のESのもとになったさらに上の先輩のESを持っている人もいるかもしれません。同じESを見たらさすがに人事もノータイムで不合格にします。
最近は情報の共有が簡単になっています。コピペなどがバレた場合にその会社だけでなく、グループ会社などに名前が共有される可能性もあると考えると恐ろしいですね。
どうしたらオリジナリティがあるESが書けるのか、ネタがないという方には、過去に書いた記事の「就活前にやるべきこと!「一番になれ」」という記事が参考になるのではないかと思います。
>>>参考記事「【理系の就活】就活前にやるべきこと!「一番になれ」」
設問ごとのESの書き方

ここからは、ESに頻出の設問について書き方のポイントをそれぞれまとめていきます。
文章の例も載せているところがありますが、私は就活生ではないのでコピペされてもノーリスクですが、同じ就活生でこのページを見ている人もいるかもしれませんので、あくまでも構成や考え方を参考にしてもらえればと思います。
志望動機
問われ方は様々ですが、基本的に必須事項であるのがこの「志望動機」です。
そして、ESを何枚書いても、慣れてきても一番苦労するのが志望動機であると私は考えています。
それでは早速、ポイントを解説していきます。
志望動機を書くうえでのポイントは以下の通りです。
- 書き出しは一文目で志望動機をまとめる
- その会社では無ければいけない理由を書く
- 将来性をプラス思考に書く
- 最後は1人称で入社後の自分と志望動機をつなげる
では、順番に詳細を説明していきます。
書き出しは一文目で志望動機をまとめる
「初めに結論を書く」ということはESを書く上での基本です。これは志望動機でも当てはまります。しかし、志望動機を書く上ではより一層気を付けてください。
志望動機には、自分の経験や社会情勢、会社の特徴など様々な背景を理由として挙げることが多いです。
これを普段話している言葉と同じように書くと、「志望理由は、~なので、~です」という形式になりやすいのです。これはESではNGです。「~なので」という部分が不要でその部分は、2文目以降に書くべきです。
例えば、私は志望動機の書き出しには「私は「○○」という思いから貴社を志望しました」という形式をよく使っていました。この「○○」の部分について2文目以降で根拠を示し、魅力付けしていくのです。
その会社では無ければいけない理由を書く
次に重要なのが他業種、競合他社ではなくその会社である必要性を書くことです。
特に競合他社との違いは意識して書かなければいけません。
なぜなら、採用担当はあなたや他の志望者が自社と同業他社とを比較し、そしてどちらにもESを出している可能性が高いことを知っているからです。
業界最大手の会社であれば、両方に内定が出ても来てくれると自信を持っているかもしれません。しかし、二番手以降は内定者が辞退する可能性を常に意識しています。
そのため、「他の内定があっても入社したい」「第一志望です」ということを志望動機の文章内で伝えなければいけません。
その会社の製品の特長、他社との違い・強みをしっかりとリサーチして文章に上手く組み込むことができると良い印象に受け取られます。
例えば、「○○という製品は世界トップシェア」「他社より品質が高い」「開発に力を入れている」などの情報を自然に一言盛り込むだけでも違います。
これらの特徴はインターネットでも手に入りますが、一番良いのは説明会の場で働いている社員に直接聞くことです。誰もが知り得る情報は武器になりません。一部の人しか知り得ない情報が就活では重要になってきます。
「いかに会社を理解してここで働きたいか」「他社ではなく、なぜこの会社なのか」根拠を持ってアピールしましょう。
将来性をプラス思考に書く
志望する会社を選ぶ際に多くの人が「(会社名) 将来性」でググっていませんか。将来性を見て会社を選ぶことはとても良いことです。
その調べて会社を志望する決め手になった「将来性」を志望動機に盛り込んでみることも有効な手段の一つです。
どの様に志望動機で書くかというと、会社の将来性に対して自分が挑戦したいことや、貢献できることを書くと良いです。
会社が将来向かう方向に対して活躍してくれる人材を採用したいので、そういう視点を持っていますとアピールすることで、面接で話し見たいと思ってもらえます。
最後は1人称で入社後の自分と志望動機をつなげる
最後の締めの文章は、起承転結の結の部分です。最後には自分はこういう考えなんだということを明確に伝えることが大切です。
最初に結論を書いた後、理由・根拠を書いて終わりになっている志望動機も多いと思いますが、それではあなた自身の考え、思いがESを見る人の頭に残りません。
最初に書いた志望動機をリマインドして、覚えてもらうつもりで最後にもう一度自分の意思を書きましょう。
書き出しの志望動機と同じ内容を言い方を変えて、強調して書けるとベストです。
私が良く使っていた最後の一文のパターンとしては、「私は貴社で○○に挑戦して、世界に○○で貢献したい」「貴社の〇〇という製品の研究開発に携わり、人々の生活を今より豊かにしたい」という形で締めていました。
終わり良ければすべて良しではないですが、最後まで志望動機を読んでくださった方にしっかりと意思を伝えましょう。
研究内容
理系で研究職、技術職を志望するとき、ほぼ100 %と言ってもよいほど問われる設問が研究内容に関してです。
「研究成果がない」「ニッチな分野で伝わらない」などと考えてなかなか書けない人も多いと思います。しかし、研究成果は他人と被ることがない、オリジナリティと経験値をアピールする絶好のチャンスなのでしっかり内容を練りましょう。
研究成果を書くうえでのポイントは以下の通りです。
- 中学生にもわかる単語を使う
- 自分の成果は何かを明確にする
- この研究が社会にどう役立つかを書く
この3点を意識することでわかりやすく研究成果を書くことができます。
中学生にもわかる単語を使う
研究の内容を正確に書こうと思うとどうしても専門用語が多くなってしまいます。しかし、あなたが思っている以上に専門用語は一般的ではありません。
ここで誤解してはいけないのが「ESは論文や学会発表ではない」ということです。研究成果を完ぺきに正確に書く必要はありません。理論的な解説などはもってのほかです。
そして、ESを読むのは多くの場合が文系出身の人事部の方です。そのため意識するべきは、義務教育の範囲の中学生でも理解できるような単語で書くということです。
研究の内容が専門的過ぎて難しいという人もいるかと思います。そういう場合は、「こんな製品に使われている」「こんな面白い特性がある」とか生活レベルに落とし込んで説明できると良いでしょう。
一例として、「メタマテリアル」についての説明を専門用語を使ったパターンと使わないパターンで書きたいと思います。
専門用語あり ver.
「 メタマテリアルとは、光を含む電磁波に対して、自然界の物質には無い振る舞いをする人工物質のことです」
専門用語なし ver.
「メタマテリアルとは、光がすり抜けるという変わった特徴があり、透明マントが実現できると言われている物質のことです」
上の例を比較するとどちらも専門外の人にとっては理解できないかもしれませんが、専門用語なしの場合の方が「何となく面白そう」ではないですか。
研究が面白そうと思われたら、研究の説明としては大成功です。
自分の成果は何かを明確にする
ESの研究内容についての設問に対して、非常に多いのが研究背景や内容の説明だけで終わっている文章です。そのような文章では企業の方が読んで「それで何が言いたいの」という感想を持つだけです。
企業側が研究内容を聞くことの意味は大きく分けて2つあります。
- わかりやすく研究成果を説明できるか
- どの様に研究に取り組んできたか
ここで意識してほしいのは2点目です。面接まで進むと実感すると思いますが、人事の方は研究内容よりも「取り組み方」「苦労したこと」「工夫したこと」などに興味を示します。
ESに上に書いたような取り組み方の姿勢などは書くのはおかしいのでやめた方が良いですが、面接で質問されることを想定してESは書くべきです。そのため、大きな研究成果よりも、自分が一番主体的に関わった研究について書きましょう。
この研究が社会にどう役立つかを書く
研究内容を書くときにもう一点意識してほしいポイントは、「研究の意義」です。
なぜかというと、面接が進むと管理職や経営幹部が出てくることが多く、彼らも面接の前にはESに目を通しています。
彼らの視点は経営者目線で物事を捉えます。そのため、彼らの視点では研究は「研究内容がどのように社会に役立つか」「いつ実現するのか」というように会社の事業として見られます。
ESを評価する人事も経営陣には頭が上がらないですし、優秀な人材を面接まで導く必要があるので、ESは社長に見せても大丈夫なようにという意識で書きましょう。
学生時代に頑張ったこと
自己PRを書く設問で最も多いのがこの「学生時代に頑張ったこと」ではないでしょうか。
学生時代に頑張ったことと漠然に聞かれる場合もありますが、以下の2項目に分かれていることが多いです。
- 学業で頑張ったこと
- 学業以外で頑張ったこと
それぞれで自分自身がいかに学生時代を有意義に過ごしてきたかをアピールして伝える必要があります。
学業で頑張ったこと
特に理系の技術職や研究職などでは頑張ったことを学業に指定されて問われることが多いです。
この設問で学業に限定して問われていることの真意としては「入社後に新しいことに取り組む能力があるか」「知識・技術的な壁に対してどう対応できるか」を見極めるためです。
そのため、学業で頑張ったことで一番NGなのは成果だけをつらつらと書くだけの自慢になることです。
私が実際にESで書いていた文章の構成としては、
- 私は、~を頑張りました
- ~に取り組むにあたり「 」を目標にしました
- 達成するために「 」の工夫・計画をしました
- 結果、~を達成しました
- 今は、さらに「 」に向けて研鑽を継続中です
という順序で書いていました。
このような構成にすることで「計画性がある」「継続して努力できる」「向上心が高い」という点をアピールできます。
実際に書くとなるとなにを書こうか迷う人もいるかと思います。しかし、「研究成果ないし…」「頭悪いから…」と悲観することはありません。就活するということは、ギリギリでも何でも大学、大学院を卒業する見込みがあるということです。ここまで苦労したことがあるはずです。自信をもってください。
学業で頑張ったことのネタはかなり限られています。(研究、資格、英語、語学、学業成績、etc.)
そのため、成果が大切なのではなく「過程」「取り組み姿勢」「工夫・計画」を重視してみてください。
学業以外で頑張ったこと
そして、一番書く内容で迷うことになるのが学業以外で頑張ったことです。この設問があることが体育会系が就活に強いと言われている要因の1つです。
真面目に学業、研究活動に取り組んできた方ほど、学業以外と言われると困ってしまうのではないでしょうか。
しかし、この設問は一番自由度が高いがゆえにESで一番差が出る部分でもあります。
この学業以外という部分ではその経験・失敗・成功から「個性・特技」「得意な役職・ポジション」「コミュニケーション能力」などをアピールすることが必要です。
また、入社後に仕事をするうえで、仕事以外に生きがいや楽しみを持っているかを見ています。特に最近は仕事で精神的にやられてしまう人も多いので、そのリスクがある人材を事前にチェックするという目的で聞いている場合もあります。
学業以外というと多くの人が書くことと言えば、
- バイト
- サークル
- 留学
- ボランティア
などです。
これらで良いエピソードを持っていればそれを存分に書いてアピールしてください。文章の構成は、上の「学業で頑張ったこと」に書いた構成と基本的には同じで大丈夫です。
ここで問題なのは、本当に書くネタが全くない人です。
よく考えて、絞り出しても本当に何も出てこないのなら、今から頑張ったことを作り出すしかないですが、何もない人は基本的にいないと思います。
- 「毎日2時間ゲームをしている」→「ゲームをする時間を確保するために作業を効率化する工夫」
- 「麻雀ができる」→「YouTubeで麻雀の研究をした」
このようにどんな些細なことでも時間を費やしたことは頑張ったことに書き換えることが出来ます。今までに多くの時間を費やしたことを思い出してみましょう。
それでも、何もなかったらあまりお勧めはしませんが、1日で作り出す裏技もあります。
それは「富士山登頂」「琵琶湖一周」など体力的につらい行動を一回でもよいのですることです。そして、これを計画し、実現するためにこんな準備したということを頑張ったこととして書きましょう。
- ~という理由で「 」を目標にした
- そのために準備、計画を立てた
- 途中で困難があり、「 」で乗り越えた
- この経験で「 」の能力が伸長した
このような構成で書ければ最低限のアピールはできます。
何でも書ける設問なだけに、工夫次第では他の志望者と差別化が図れ。非常に高い評価を得ることが出来る可能性があります。時間をかけて考えてみましょう。
会社で取り組みたいこと、志望職種
この設問は志望動機にも近いですが、志望動機とは別に問われることも多いのでしっかり想定して準備することが大切です。
ここでは、「具体的に会社で働く姿がイメージできているか」「求める人材とマッチしているか」をチェックされています。
多くの会社は採用活動をする場合、どの部署、どの職種に何人ずつの人材を採用するという採用目標を決めています。そのため、ミスマッチを防ぎ、入社後の配属まで考えて、学生がどのような仕事をイメージしているかを把握してから採用します。
そのため、ここでは具体的な仕事内容まで踏み込んで書く必要があります。
書く前にまずは情報収集ですが、仕事内容や会社内での部署・職種はインターネットでは詳細にわからないことが多いです。会社説明、インターンシップに行って働きたい部署の社員から話を聞きだすのが一番です。
情報、自分の希望が決まったらESにそれを詰め込みます。
私は以下の流れで文章を構成していました。
- 私は、~に挑戦したい
- なぜなら「 」という思いを持っています
- 貴社の製品(技術)は「 」という特徴がある
- それをさらに「 」したい (社会背景などから、今後する必要がある)
- そのため「 」という業務で~に挑戦したい
多少、会社によって構成は変えますが、基本の型としては上を意識していました。
就活では内定を獲得することももちろん大切ですが、入社後の配属や職種の希望を伝える機会であることを忘れずにESや面接に臨んでください。この設問はまさにそれを伝えるタイミングです。有効に活用しましょう。
会社であなたの強みをどう生かすか
ESでは長所や短所を問われることも非常に多いです。その中でも書くのが難しいのはこのように仕事と絡めた聞かれ方をする設問です。
この設問に対しての文章を書くときには、自分の長所と実際の業務内容を上手く繋げることが大切です。短い文章の中で長所の裏付けや根拠(エピソードがあるとなお良い)を入れ込みつつ、会社での仕事にそれを適応できるとアピールすることは非常に難しいです。
評価される効果的な内容を書くためには、情報収集が必須になると共に自己分析も必要になります。嘘で塗り固めることは簡単ですが、面接や入社後にボロが出て苦しむのは自分自身です。
この設問に対しては、以下の構成で書いていました。
- 私は、「 」という強みを生かして貴社で~を実現したい
- 私は「 」という経験から「 」という強みを持っています
- 貴社の製品(特色)は「 」で、更なる向上(維持)には~が必須だと考えている
- その実現ためには「 」が必要で私の強みである「 」を生かして~の実現に挑戦したい
このような構成で、会社や製品の特色の理解度を示し、会社で自分自身の仕事の立ち位置を明確にすることを意識していました。
もしESに「長所・短所」が文章ではなく単語や一言で書くような形式になっていた場合、面接で「それをどう生かせるか」を聞かれることが非常に多いです。
このような設問は特にESに書くときには面接までつながっていることを意識して書くようにした方が良いです。
終わりに
ESは就活で企業と関わる入り口です。入り口をくぐる前には準備・情報収集をすることが大切です。就活に正解は無いので、是非この記事も参考にして自分自身の必勝法を作り出してほしいです。
私が一番ES、面接で心掛けていたことは「嘘偽りなく、自分をさらけ出す」ということです。
就活は一瞬ですが、入社後は長い社会人生活が待っています。不用意に背伸びして入ってしまった会社では押しつぶされてしまいます。
皆さんが自分らしさを 無理せず自然に発揮できる企業を見つけて入社できることを願っています。